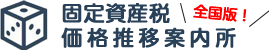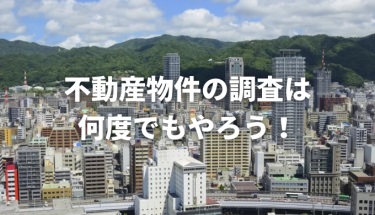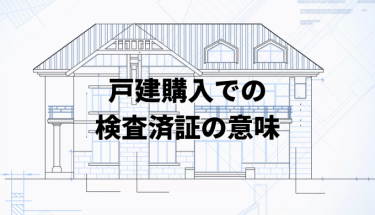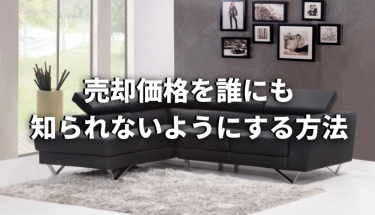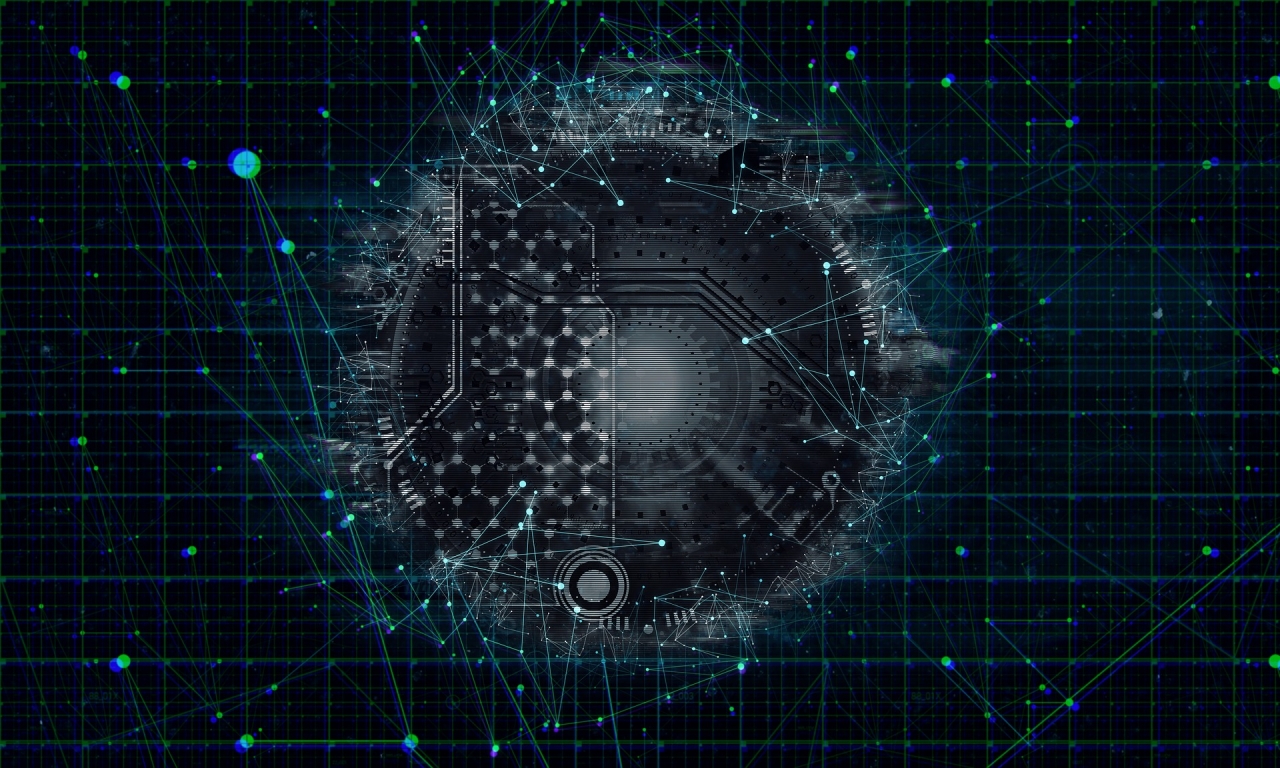中古マンションを購入するときの諸費用について

ここでは、中古マンションの諸費用についてご説明します。
【契約関係】
(1)印紙代
売買契約を締結するときに、売買契約書に貼付して、割印をします。売買金額によって、印紙代は違ってきます。
具体的な金額は、 国税庁印紙税を参照ください。
また、不動産の売買の場合は、印紙税の軽減がありますので、国税庁印紙税の軽減のところを参照ください。
(2)登記費用
登記費用には大きく分けて、登録免許税と司法書士の報酬に分けられます。
登録免許税は所有権移転登記、ローンを利用する場合の抵当権設定登記等をする際にかかってきます。
登録免許税の金額は、固定資産評価額によって異なりますので物件が特定されるまでわかりません。
その物件の「評価証明書」があれば司法書士に見積もりを取ることができます。
(一般的には、不動産屋に頼めばやってくれます)
司法書士の報酬には、所有権移転登記、抵当権設定登記等にそれぞれかかります。
また、事前調査費用、日当などがかかってきます。
登録免許税と、司法書士の報酬をあわせたものが、登記費用と呼ばれます。
マンションで一般的な80平米ぐらいのもので約30~40万円ぐらいです。
(3)清算金
固定資産税(都市計画税も含む)と、マンションの管理費・修繕積立金を、売主、買主間で日割り清算をします。
関東は、1月1日が起算日で年末までを1年とします。
(関東で売却するときは、年末までの分しかもらえなかったのに、関西では翌年の3月末までの分を払わないといけないので・・・)
(4)仲介手数料
「売買代金の3%+6万円」に消費税を加えた金額がかかります。
「それは上限でしょう?」と言い返してみてください。
(5)不動産取得税
物件次第ですが、アバウトにいいますと、 新築であれば大抵はかかりませんが、豪邸になるとかかります。
中古のマンションの場合は築25年までは軽減があるので、かかっても少しだけです。
【ローン関係】
(1)事務手数料
銀行によりますが大体31,500円のところが大半。
諸費用ローンをあわせて利用する場合は、もう31,500円かかるときがあります。
(2)保証料
返済期間によって違います。
たとえば35年返済の場合は、100万円当たり20,620円です。
3,000万円の融資の場合の保証料は3,000÷100×20,620円=618,600円
(結構高いですよ。また、借り入れ金利に0.2%上乗せすると、免除にすることもできます。)
(3)火災保険料
マンションで古すぎなければ大体15万円くらいあれば35年くらいの期間は入れます。
(4)印紙代
金銭消費貸借契約書に貼付するものです。 国税庁印紙税を参照ください。
(いわゆるローン契約、銀行とお金を融資してもらう契約をするときにかかります。)
以上、上記の【契約関係】【ローン関係】の金額を足した金額は、簡略化して計算する方法があります。
物件価格のだいたい8%ぐらいです。
(不動産屋の新人は8%で計算します。というわけでだいたい8%あったら足りるのですが、古い物件で800万円とか1,000万円強くらいの物件の場合は、10%を超えるときもあるので、要注意です!不動産屋の新人はこれで失敗してお客さんからの苦情を受けることもあります)
【その他費用】
(1)引越代
(2)カーテン・照明・エアコン・家具・電化製品など
中古マンションの諸費用(登記費用、仲介手数料など)について

- 登記費用
- 仲介手数料
- 住宅ローン借入に際しての諸費用
- 固定資産税の清算金
- 管理費の清算金
- 不動産取得税
- 印紙代
- 火災保険料
これを支払う時期ごとに分類すると、
売買契約締結時
- 印紙代
- 仲介手数料(全体の半分)
引渡し(残代金決済)時
- 住宅ローン借入に際しての諸費用
- 固定資産税の清算金
- 管理費の清算金
- 火災保険料
引渡し後
- 不動産取得税
となります。
印紙代については売買価格によって税額が違いますので、その都度国税局のホームページなどでご確認ください。
次に仲介手数料ですが、仲介手数料は売買価格によって不動産業者が受領してもよい上限が法律で定められています。
一般的に知られている「3%+6万円」というのは速算式で、
「6万円は消費税?」などと聞かれることもありますが、実際にはそうではありません。
売買価格の200万円から400万円までの部分・・・4%
それ以上の部分・・・3%
となっているのです。
例えば1000万円の物件の場合、
|
合計は10+8+18=36万円となります。
400万円を超える場合の速算式が「3%+6万円」で、1000万円の場合は、
1000万円×3%+6万円=36万円となります。
そしてその36万円に消費税が加算され、消費税率を8%とすると
36万円×1.08=388,800円
となります。
一般的には、その手数料の半分を売買契約時に支払い、残りの半分を残代金支払(決済)時に支払うことになっています。
そういうわけで、 売買契約締結時には、
・印紙代
・仲介手数料(全体の半分)が必要になります。
これはそんなに難しくありませんね。
次回は引渡し(残代金決済)時についてご説明したいと思います。
・管理費の清算金
・火災保険料
についてご説明していきます。
ただ固定資産税と違うのは、固定資産税は元になる金額が1年分であるのに対して、管理費は1ヶ月分が対象です。
また管理費の場合は管理会社の引き落としの日程と、引き落としの銀行での手続きのタイミングによっては、引渡しをした月の翌月分が、売主の口座から引き落としされてしまうことがよくあります。
そのため、管理費の清算は引渡しの月だけでなく、その翌月の1ケ月分まるまる買主から売主に支払っておいて、売主の口座から引き落とししてもらうことが頻繁にあります。
火災保険には入るべき

つぎに「火災保険料」です。
火災保険は通常、任意に加入するものですが、住宅ローンを銀行から借りる場合、銀行が「必ず火災保険には加入してくださいね」と言ってきます。
この「加入してくださいね」はとても意味深です。
正確に説明しますと、
という意味なのですが、
銀行が住宅ローンの借入本人に、火災保険に共性的に加入させることは、どうやらダメなことのようなのです。
ひと昔前では、銀行の提案する保険に強制的に加入させられ、おそらく銀行には保険会社からのコミッションがあったはずです。ですが、最近の銀行は強制をしてきません。
それを遠回しに「火災保険には必ず加入してくださいね」と言っているのです。
うまく行けば銀行で火災保険に加入してくれることにもなり、コミッションが入るのと、担保が消失しても銀行は損をしないようにできることになります。
成績にシビアな銀行ならではですね。
というわけで、火災保険は実際に火災が起きた時には本当に困ってしまうので、加入しておいたほうが良いと思います。
マンションの場合は長期で入っても数万円ですが、木造一戸建てとなると、35年などの長期で加入すると数十万円になります。50万円を超えることもあります。
その場合は期間を10年にするとか、家財の保険のオプションを付けないとか、いくつか提案してもらうとよいでしょう。
資金計画を立てる際には、マンションの場合15万円程度、戸建の場合50万円程度予算を取っておけばよいかと思います。