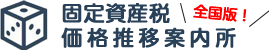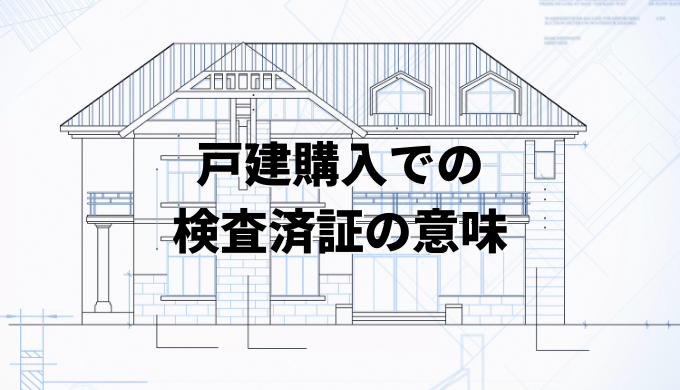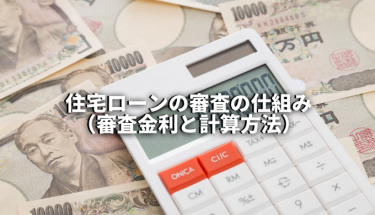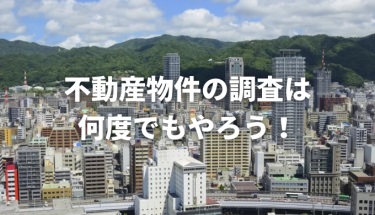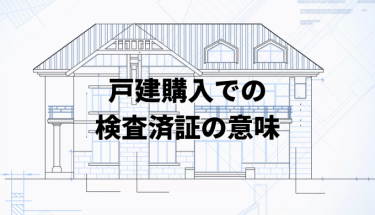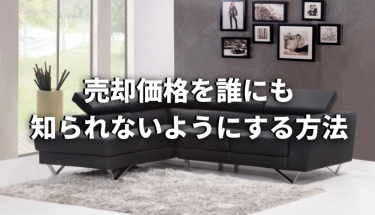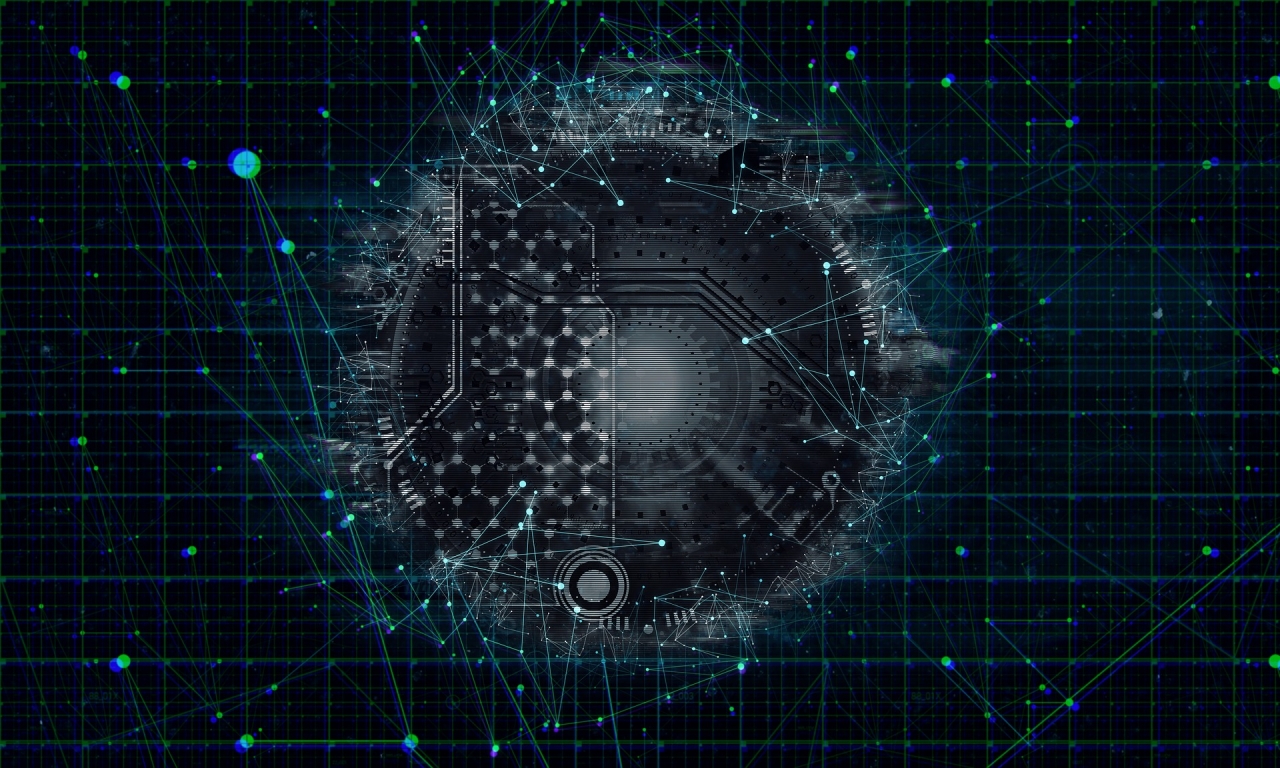検査済証の意味

物件の資料を見ていても、
親切な資料には「検査済証はありません」「検査済証なし」などと書いてありますが、
物件資料の項目にも検査済証の有無の項目はありません。
最近の新築一戸建では、検査済証を取るのはあたりまえになっていますが、
一昔前では検査済証を取るということは、あたりまえではなかったのです。
大手ハウスメーカーでさえもとっていないケースも何度もみました。
新築戸建の場合、この検査済証がないと、銀行は住宅ローンを融資してくれません。
それもひと昔前は融資をしてくれていたのですが、ここ最近ではだめです。
融資してくれません。
ですから、新築で検査済証がまだ発行されていない状態で売買をする時、
例えば未完成物件の時などは、不動産売買契約書の特約欄に、
「売主の責任と負担において検査済証を取得し、買主に交付するものとする」というように書いたりもします。
ですが、中古一戸建の場合は、その「ひと昔前に」建てられているものですから、
検査済証が当たり前に取得されていないことがよくあるのです。
その場合、住宅ローンは融資してもらえるのでしょうか。
先に答えを申しますが、住宅ローンは融資してもらえます。
しかし、住宅ローンを融資してもらえたとしても、物件に対しての不安は残ります。
検査済証の有無が示すのはどんなことなのかをもう少し詳しくご説明させていただきます。
その建築計画が法律、条例に適合しているのか役所がチェックし、合格しないと建築はできません。
そのチェックする作業を「建築確認申請」といいます。
そしてその建築確認申請の内容(図面など)を役所、もしくは役所の指定する機関がチェックし、
合格すると「建築確認済証」が発行されます。
そして工事が完了したあとに、役所に申請をし、「完了検査」を受けるのですが、
ひと昔前はこの完了検査を受けていない住宅が非常に多かったのです。
完了検査に合格すると、「検査済証」が発行されますが、
検査済とは先程の「建築確認済証」の通りにきちんと建築をしたのかどうかの検査なのです。
設計段階できちんとした設計がされているかどうかは建築確認済証でチェックすることができますが、
そのとおりに建てたかどうかを確かめるには、あらためてチェックしないとわかりません。
検査済証のない建物は合法の建物であるという根拠はない

完成後施主が申請すれば、役所がチェックしにきます。
そして申請通りに建てられていた場合は「検査済証」が発行されます。
簡単に言えば、検査済証のある建物は、合法であるというお墨付きを貰ったことになりますが、
検査済証のない建物は、その確証がなく合法の建物であるという根拠はなくなります。
建物の強度を満たしていたとしても、検査済証がないと、その通りに建ててあるという確証がないのです。
もしも、その物件を購入する際に、金融機関が融資してくれたとしても、
もしかしたら柱が一本足りないかもしれない、
もしかしたら耐震基準を満たしていないかもしれない、といった不安要素が拭えません。
次は更に具体的にご説明したいと思います。
例えば建ぺい率、容積率です。
建ぺい率、容積率は建築基準法によって数値が定められています。
設計の段階、建築確認申請の段階で、
作成した図面をもとに役所や役所の指定機関は、建ぺい率、容積率を当然チェックします。
それをクリアして初めて建築確認済証が発行され、建築の許可が下りるのです。
ところが、ひと昔前には、検査済証の発行申請をしなくとも、
罰則はありませんでしたし、金融機関の融資も実行されていましたので、
建築確認申請の時にはきちんと合法の申請をしておいて、
実際の建築の際には全く違った建物を建てるような悪質な行為もあったのです。
もう少し突っ込んでご説明していきますと、登記簿謄本(登記事項証明書)を見ますと、
登記されている土地面積と建物面積を確認することができますが、
時々その土地面積と建物面積で計算をすると、建ぺい率や容積率がオーバーしていることがあるのです。
たとえば掘り込みガレージなどが登記されているときです。
掘り込みガレージは建物の登記面積に算入されることがあります。
掘り込みガレージの面積全部が登記されます。
これは建築確認申請の概要書などを見れば記載されています。
当然、建築確認申請図面にも記載があります。
ですから登記面積では容積率をオーバーしていたとしても、
建築基準法に照らし合わせると容積率はオーバーしていなかった、
ということはよくあることなのです。
掘り込みガレージはほんの一例ですが、
マンションの場合などは共用部分の廊下などが容積率の計算の際の面積に算入されないなどの特例措置などもあります。
違法建築ではないのが「検査済証」

そこで役に立つのが検査済証なのです。
登記面積で計算すると容積率オーバーなのに、違法建築ではないと言い切れるのが「検査済証」なのです。
ですから、登記簿を見て容積率や建ぺい率がオーバーしていないかをチェックするのはとても大切でありますが、
同時に建築確認申請の建築計画概要書というものを役所で閲覧、
またはコピーし、検査済証が発行されていたかどうかを確認する作業がとても大切になります。
ちなみに重要事項説明書にはその項目が必ずありますので、検査済証がない場合、
その物件を購入するか否かよく考えてお買い求めいただくとよいでしょう。
申請通りに立てているにもかかわらず、何らかの事情で検査済証の申請をしていないこともあります。
阪神淡路大震災のあとの建築ラッシュの時などは、
大手の誰もが知っているハウスメーカーでも検査済証を取っていない物件があります。
一戸建てを探しておられると、
一度はセットバックという言葉を聞かれたことがあると思われますが、
このセットバックや私道負担という言葉を知ってはいても、キチンと理解されていない方がとても多いです。
まずは、セットバックについてお話しします。
敷地の道路側部分の一部を道路として取り扱い、道路に提供することです。
前面道路が将来的に4m以上となるように、
道路の中心から測って2mのラインまでに含まれる敷地の部分を道路として提供するものです。
例えば前面道路が3mで、道路の中心がその3m道路の中心だとしますと、
道路の中心から、現在の道路と敷地の境界線までは1.5mとなります。
そうすると、道路の敷地境界のところから敷地側に0.5m分を道路として提供しないといけません。
仮に間口が10mだとすると、0.5×10=5平米もセットバックすることになります。
このセットバックラインを決定するのは、建築確認申請のときになります。
建築確認申請の図面を作成し、その図面に道路の中心線とセットバックラインを記載します。
このセットバック部分の面積を除いた面積がとても重要です。
特に建ぺい率、容積率いっぱいいっぱいに建築する際は、この面積が減ったりしてしまうと、
建ぺい率や容積率がオーバーしてしまい、違法建築物にもなりかねません。
セットバックと検査済証の関係性
そこで検査済証の話になりますが、セットバックをして建物が建築されたあとに、
役所による検査を受けてセットバック済であることも確認してもらいますから、
検査済証があればセットバック済みであることが確認できるのです。
しかし反対に検査済証がないとなると、セットバックをした根拠を失ってしまいます。
もしかしたら、道路の中心線を再度見直してさらにセットバック、なんてことにもなりかねません。
セットバックが必要な道路である場合は、特に中古一戸建ての場合、検査済証の有無を確認しましょう。
セットバックをして検査を受け、検査済証が発行されてから、さらに工事をしてしまう人もいます。