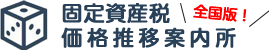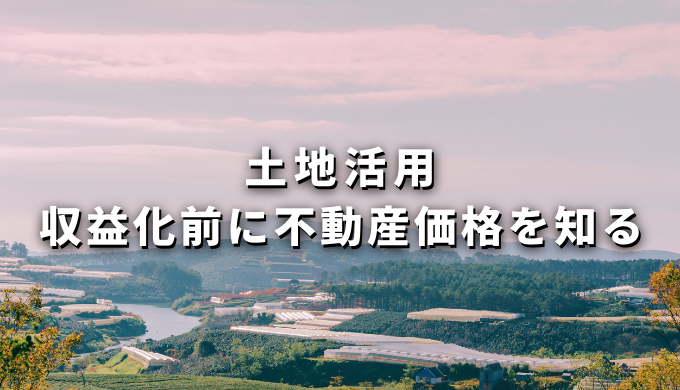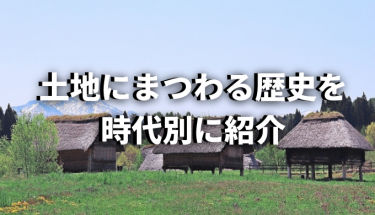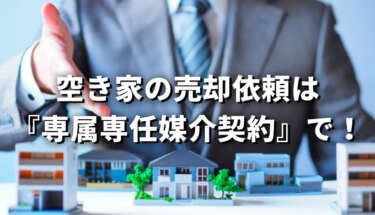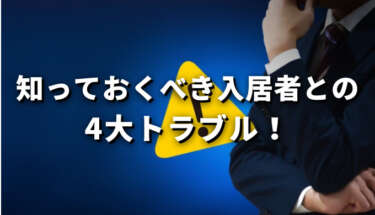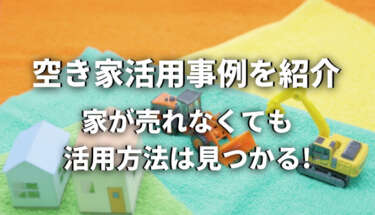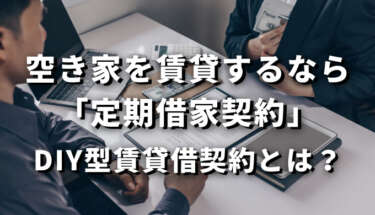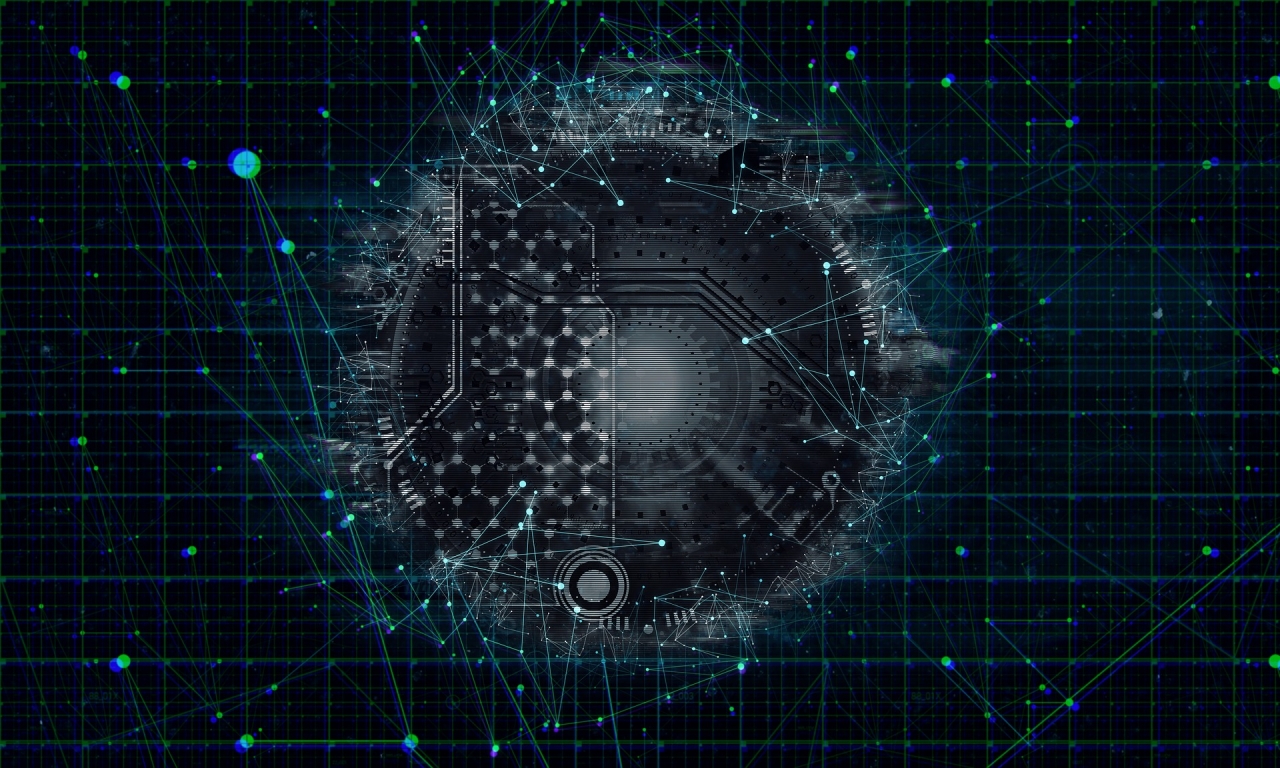土地活用の前に、そもそも、不動産の価格はどうやって計算するの?
不動産の価格っていったいどうやって求めるのでしょうか?

やっぱり、それは過去の取引価格を参考にするんじゃないの?

うん。確かに、それもひとつの方法だね。
じゃぁ、今回は、不動産・土地の価格算定方法について教えてあげよう。
じゃぁ、今回は、不動産・土地の価格算定方法について教えてあげよう。
国土交通省が発表している、不動産鑑定評価基準においては、
不動産鑑定評価基準3つ
- 不動産に対して認められる効用
- 不動産の相対的稀少性
- 不動産に対する有効需要
のそれぞれが相関して生まれる経済価値を、貨幣に置き換えて表示したものと言っています。
土地の価格は地価と言いますが、この算定方法には
- 原価方式
- 比較方式
- 収益方式
の3つがあります。
資産評価の方法を詳しく見ていこう

原価方式
原価方式とは、不動産の再調達に要する費用に着目して不動産価格を求めようとする方法です。
不動産を立てるのに、どれくらいの費用が掛かるかという点を重視して算定する方法ですので、ビジネスシーンにおいて原価を算出するコスト・アプローチに似ています。
不動産を立てるのに、どれくらいの費用が掛かるかという点を重視して算定する方法ですので、ビジネスシーンにおいて原価を算出するコスト・アプローチに似ています。
取引事例比較法
多数の取引事例から、類似の物件の取引を選択し、地域・個別の要因を修正したうえで、比較を行って不動産価格を求める手法です。
類似の物件の取引事例から算出する点は、ビジネスシーンにおけるマーケット・アプローチと同じとも言えます。
類似の物件の取引事例から算出する点は、ビジネスシーンにおけるマーケット・アプローチと同じとも言えます。
収益還元法
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益から不動産の価値を算出する方法。
この収益還元法の中には、一定期間の純収益を還元利回りによって還元する「直接還元法」と、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する「DCF(Discounted Cash Flow)法」の2方式があります。
直接還元法とは、
収益価格 = 1年間の純収益 ÷ 還元利回り(一般的住宅5~7%、事業用8~10%が目安)で算出します。
収益価格 = 1年間の純収益 ÷ 還元利回り(一般的住宅5~7%、事業用8~10%が目安)で算出します。

純収益ってなに?

収益から経費を差し引いた実質的な利益のことだよ。
企業の決算情報でいうところの純利益と同じだね。
企業運営にもいろいろな経費がかかるけど、不動産所有にも修繕費や固定資産税などの経費が掛かるからね。
企業の決算情報でいうところの純利益と同じだね。
企業運営にもいろいろな経費がかかるけど、不動産所有にも修繕費や固定資産税などの経費が掛かるからね。

なるほど。

でも、純収益がずっと一定であるというのは、現実的じゃないよね。
そこでその課題を解決するために考えられたのがDCF法です。
ビジネスシーンにおいても、企業の株価を算出する際にDCFなどを使用しますが、これと同様に将来の収益を現在の価値に置き換え、割り引く算出方法です。
ビジネスシーンにおいても、企業の株価を算出する際にDCFなどを使用しますが、これと同様に将来の収益を現在の価値に置き換え、割り引く算出方法です。

む、、、むずかしいな。。

じゃあ、今月発生する100万円の家賃収入と、10年後に発生する100万円の家賃収入はどう違う?

同じ100万円だから、同じだと思うけど、どう違うの?

今100万円があれば、これを投資に回すことだって可能だよね。そうすれば…、
年利5%で運用できた場合、
- 元金1,000,000円・利率5%/年
- 期間1年
- 運用満期時105万円

という計算になるんだ。

うん確かに。 なるほど、1年後には105万円になっているから、1年後の100万円の家賃収入と同じ価値じゃないんだ。

そういうことだね。
お金には金利がつきものだから、こういう考え方はとても重要だと思うので覚えておくといいよ。
お金には金利がつきものだから、こういう考え方はとても重要だと思うので覚えておくといいよ。
バブル崩壊後、地価は必ず値上がりするという「土地神話」も崩れ去りました。
このため、取引事例比較法ではな不十分で、土地活用により生み出される【収益】に着目して地価を算出するようになったんです。
このため、取引事例比較法ではな不十分で、土地活用により生み出される【収益】に着目して地価を算出するようになったんです。

確かに、バブル崩壊後は、取引事例なんてあてにならないもんね。

うん。現在では、土地活用から生み出される収益によって地価が変動するようになったわけだね。
こういった意味でも、収益は、単純に投資のテクニックだけではなく、その土地の周辺環境や、インフラ、人口など、様々な要素が複雑に絡み合って生まれるものであると、再認識しておくことが重要です。
地価には5つの種類があるので、しっかり覚えておこう

5つの地価をしっかり把握して、それぞれの目的に応じた正しい利用方法を選択しましょう。
1:実勢価格
実際に市場で取引されている土地価格のことです。
土地活用を実施しようとしている地域で、実際に取引されている価格を調べておきましょう。
土地活用を実施しようとしている地域で、実際に取引されている価格を調べておきましょう。
もちろん重要なのは、その地域の将来性や、どのような業種が進出しているのか、若者の人口は増加傾向か、それとも高齢者層が増えているのか、なども綿密にチェックしておくことです。
重要ポイント
公示価格や路線価では高い評価を得ていても、実際の取引はほとんど皆無の地域があることです。
需要と供給があって初めて、取引は成立するものですから、何らかの理由で取引が少ないということは、何か問題をはらんでいる土地である可能性があります。
この要因も含めしっかり把握しておきましょう。
需要と供給があって初めて、取引は成立するものですから、何らかの理由で取引が少ないということは、何か問題をはらんでいる土地である可能性があります。
この要因も含めしっかり把握しておきましょう。
ただし、この実勢価格を正確に把握することは難しいことです。
地元の不動産業者に聞いたり、改めて遊休地を訪れ、しっかり地域の活気を肌で感じることも重要です。
地元の不動産業者に聞いたり、改めて遊休地を訪れ、しっかり地域の活気を肌で感じることも重要です。
2:公示価格
国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価を設定する目的で、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示しています。
公示価格には以下の目的があります。
- 一般の土地取引の指標
- 不動産鑑定の基準
- 公共事業用地の土地取得の際の基準
- 土地相続評価の基準
- 固定資産税の基準
3:基準地価格
都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定し、9月中旬に公表されます。
土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。
4:路線価
国税庁が毎年1月1日に道路に面した土地の価格を調査し、7月上旬頃に公表します。
路線価は、土地の相続税や贈与税の課税価格の目安となるもので、公示価格の80%が水準となっています。
80%というのがポイントで、
A地点の公示価格が10万円で路線価が8万円のとき、B地点の路線価が12万円だったら、B地点の15万円だと推測できますね。
また、公示価格や基準地価格は点ですが、路線価は道路に沿って評価しているので、市街地であれば、ほぼ全ての土地の評価を調べることができます。
路線価で注意が必要なのは、方角の区別をしないで道路を評価しているときです。

方角を区別していないと何が問題なの?

たとえば、アパートを建設する場合に、用地が南側の道路に面していれば、住戸も南向きとなり高い賃貸価格を設定することができるよね。

そっか。日当たりや、日陰はアパート経営にとても重要だもんね!
このように、土地活用によって土地の価値が変わるので、路線価も一つの目安として認識しておきましょう。
5:固定資産税評価額
固定資産税は、毎年1月1日に、現在の土地・家屋等の固定資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに税額を算定して市町村が課税する税金です。
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事・市町村長が決定し固定資産課税台帳に登録したもので、固定資産税評価額といいます。
評価額は、3年に1度、評価が変わり基準年度としています。
直近では、2018年度がこの基準年度にあたりました。
バブル以前は公示価格の30%程度の評価でしたが、現在では公示価格の70%を基準に評価されています。