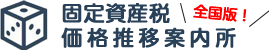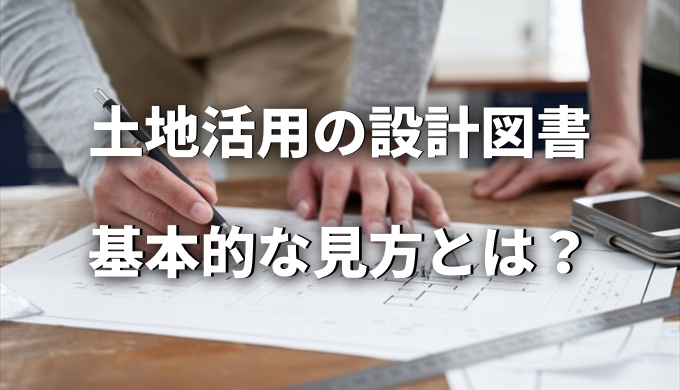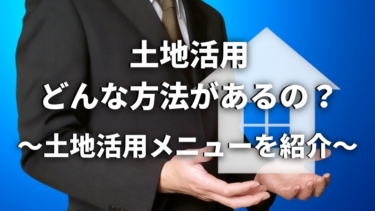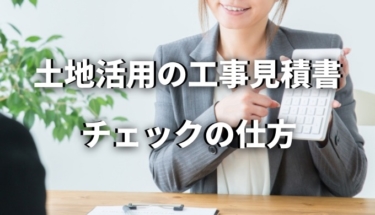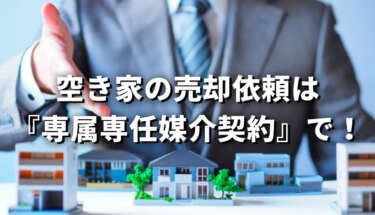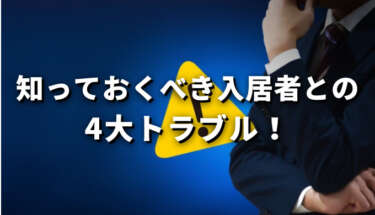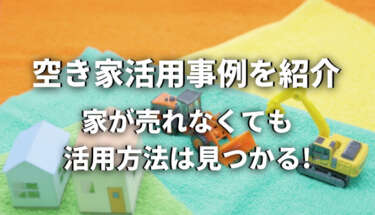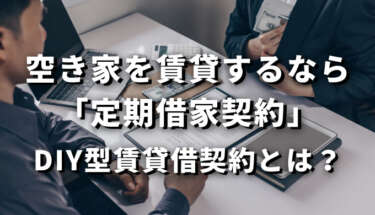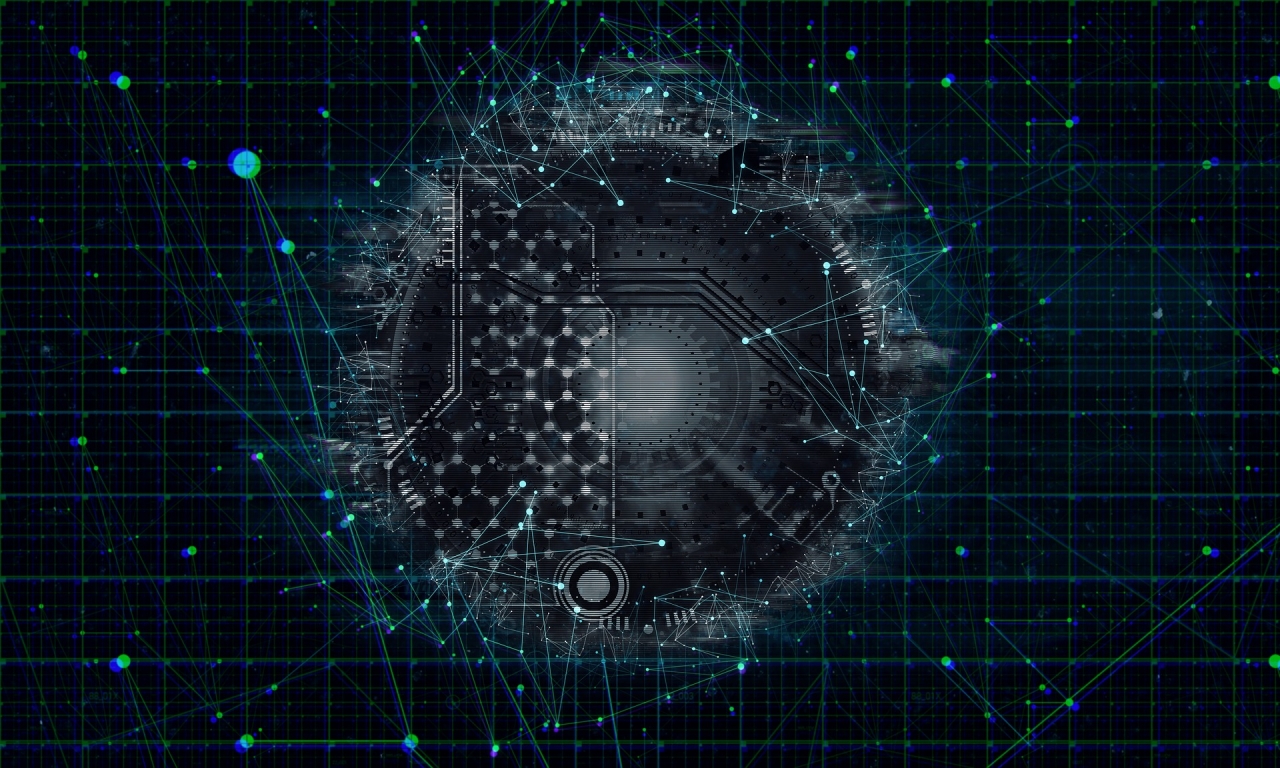土地活用の設計図書とは?


設計図書作成の流れ
- 基本設計図
↓ - 実施設計図(配置図・平面図・立体図・断面図・仕上表)
↓ - 施工図
↓ - 竣工図
土地活用の建物のコンセプトやデザイン、品質は設計図書に表されています。
建物の設計図は、法令上の制限を全て遵守してつくられているものとなります。
始めにイメージを表現した「基本設計図」がつくられ、プランや総事業費、賃料などを検討した後、事業で採用する「基本図面」を決めます。
その後、「実施設計図」を作成し、建物が竣工したら実施設計図を修正して「竣工図」を作成するという流れとなります。
- 建物のエントランスの配置
- エントランスから2、3階に行くアプローチ
- 各フロアーホールの位置、大きさ
- 各住戸に入るまでの廊下
- 外付けバルコニー
実施設計図を細かく確認しよう!
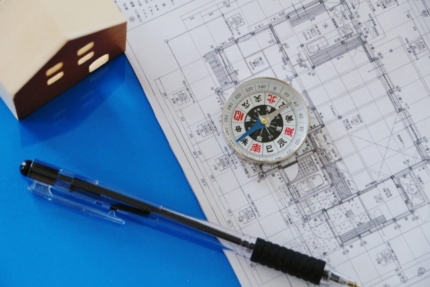
基本設計図の後に作成される「実施設計図」は、建物を建てる直前の設計図となるため、確認しておきたいポイントが沢山あります。

① 配置図の確認ポイント!
配置図とは、建物と敷地の位置関係を示す図面で、道路と敷地、外構(造園)や通路などの計画図と一緒にしてあり、 1階の平面図を兼ねているのが一般的となります。
確認ポイント
- 道路・横断歩道と敷地・建物との位置関係を確認
- 道路と建物の高低差を確認
- 敷地周辺の高低差を確認
- 建物床の高さを確認
- 道路から建物エントランス・駐車場・駐輪場・非常階段などへのアプローチを確認
- 駐車台数を確認
- 敷地内に設置されている受水槽・キュービクル・散水栓・マンホール・枡を確認
- 外構(門・塀・擁壁・植え込み・舗装・排水溝など)を確認
- 植栽計画を確認
配置図と植栽計画図が別図になっていることもありますので、よく確認してください。
② 平面図の確認ポイント!
平面図には、 1階、基準階などの各階の平面プランが用意されます。
確認ポイント
- エレベーターや階段の位置を確認
- 廊下の長さを確認
- 柱の位置を確認
- 事務室や各住戸の形状を確認
- 入口の扉の位置の確認
- バルコニーの形状を確認
1階の平面図には、エントランスやエレベーターなどのレイアウトが表現されているため、建物のグレードがこの平面図でわかります。
また、2階、3階、4階、5階はほぼ同じような平面計画になることが多く「基準階」と言われています。
基準階の平面図の場合「2階~5階」と表記されて、同じ平面図で処理されることがあります。
ただ、上階は道路斜線、日影規制等によって床面積が削られることがあり、階数ごとに平面図が変わる場合こともあります。
平面図には、窓、採光、外階段・外廊下、バルコニーやエントランスの「全体の配置」や各住戸の大きさが描かれているため、配置図と平面図を見てどのような建物となるのかをイメージすることができます。
1階を店舗として使用する場合は特に、道路からの見栄え、エントランスからのアプローチ、店舗内の柱やトイレの位置などについて、顧客動線を考えながら検討する必要があります。

③ 立体図の確認ポイント!
立面図は基本的に東・西・南・北の4方向の図面で建物の外観を表しています。
確認ポイント
- 道路側正面から見た建物の全体像を確認
- 南向きの日照条件の良好な住戸数を確認
- 日照や眺望の条件が厳しい住戸数を確認
- 道路斜線などで面積が削られている住戸を確認
道路側正面から見た建物の全体像(ファザード)は入居者の第一印象を左右する場所となりますので、要チェックポイントとなります。
④ 展開図の確認ポイント!
展開図は、部屋の中心に立って東・西・南・北を見た住戸内の姿が表されていて、各部屋の構造や構成がわかるようになっています。
確認ポイント
- クローゼット・ドア・窓の位置を確認
- クローゼット・ドア・窓の大きさを確認
展開図を見れば、設計上のミスをチェックすることも可能となります。
バルコニー側の窓が腰までしかないなどのミスがある場合もありますので、しっかりチェックしましょう。
⑤ 設備図の確認ポイント!
設備図は、給排水、給湯、ガス、電気、冷暖房など、住宅設備機器の配線・配管・機器や器具類の設置位置を平面図上に示した図面を総称したものです。
設備図は設備ごとに図面を作成しますが、小規模の建物では給排水と給湯・ガス設備を1つの図面にまとめた「給排水設備図」としたり、電気・電話・照明・換気扇などを示す「電気設備図」を作成する場合もあります。


でも、設計図書について土地オーナーがわからないことは、設計事務所や土地活用プランナーなどのプロに確認をお願いすることも大事になるんだよ。
設計図書に出てくる床面積とは?


詳しく説明しよう。
3種類の面積
- 施工床面積
- 法廷床面積
- 法廷床面積以外の共用部分
① 施工床面積
施工床面積は、実際に工事される面積のことです。
「専有面積(賃貸可能部分)」「法定床面積に入る共用部分の面積」「法定床面積以外の共用部分の面積」3つの合計が「施工床面積」となります。
② 法廷床面積
法廷床面積は、「専有面積」に「法定共用部分(容積率にカウントされる法令上の共用面積)」をプラスしたものです。
法定床面積は主に、建物の面積をチェックする時に使われます。
③ 共用部分
法廷床面積以外の共用部分は、法令上面積にカウントされない共用部分の面積のことを言います。
外階段やエントランス、バルコニー、駐車場等の床面積などが、法廷床面積以外の共用部分となります。
床面積からレンタブル比を確認しよう!
建物全体の床面積に占める専有面積(賃貸可能面積)の割合をレンタブル比と言われています。

通路などを工夫して共用スペースを最小限にすればレンタブル比は向上します。
レンタブル比の数値をチェックして効率化を工夫することも重要となります。
設計事務所の中には、レンタブル比を念頭に事業の採算性を意識して作図し、効率の良い建物としてくれるところもあります。
レンタブル比の計算式
分母の法定床面積を、施工床面積、容積対象床面積に替え、3種類のレンタブル比を算出することで、設計の効率性がより正確に把握することができます。
しかし、レンタブル比の数値ばかり気にして、必要な共用部分を貧相にしてしまうと、入居者の印象は悪くなってしまいます。