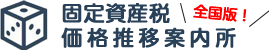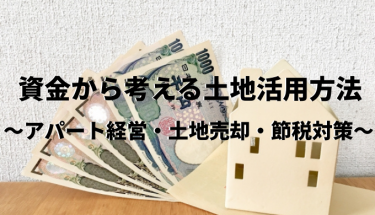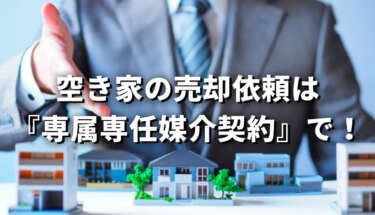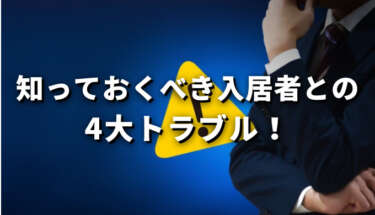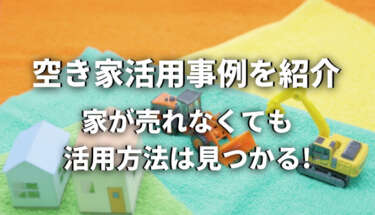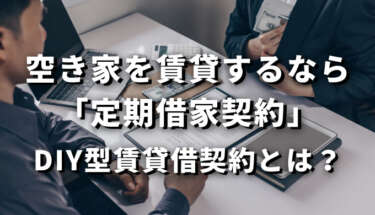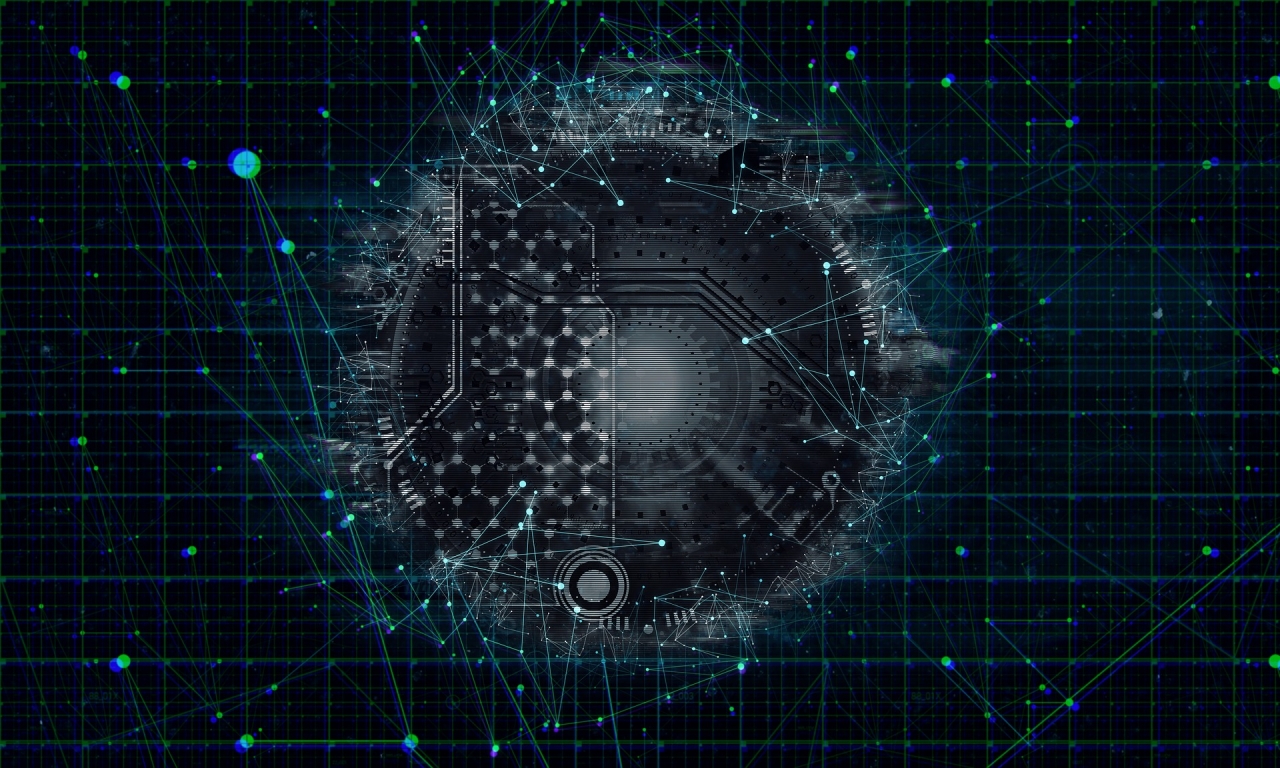土地活用の前にチェックすべき様々な指標

住宅金利の動向をチェックする重要性
好景気と不況と金利を把握しておこう
土地活用と金融は密接に関連していて、自己資金だけでアパートを建てたり、投資用マンションを購入するケースは稀でしょう。
ほとんどの土地活用で多額の借り入れを行うため、金利の動向には注意を払う必要があります。
金利の水準は、好景気の時には資金需要が増えるため、金利は上昇し、不況時には金利は下降する事になります。
これは一般サービスと同様に、金利にも需要と供給の原理が働いているためと考えられます。
投資メリットがあるかないかの判断を金利で行う場合
金利が低ければ預金メリットは低いですが、低利で融資を受けることが出来るので、投資家目線では投資を行いやすくなるので、投資のタイミングかもしれません。
海外投資家の目で見ると、金利の低い通貨を保有するメリットは少ないので、通貨の価値が下がるため、輸出が増え輸入が減る傾向にあります。
投資が活発になり、景気が上昇することもあり、この場合、投資対象として通貨が対象になるケースや、将来のインフレ率の上昇を見込んで、長期金利が上がる場合もあります。


インフレ率を求めるには
消費者物価指数を求めて、以下のように求めます。
このインフレ率が例えば1%の場合、年率1%の収益を確保しないと、現在の生活は維持できません。




逆に、金利が高くなると、預金のメリットが上がるんだけど、融資を受けて投資にまわすリスクが上がるので、投資意欲は下がる傾向にあります。
海外の投資家からみると、金利の高い通貨を所有するメリットが高いので、通貨の価値が上がって輸出が減り、輸入が増える傾向になります。
金利の上昇は、加熱した景気を冷ます効果があります。
短期金利と長期金利について理解しよう
金利は大きく短期金利と長期金利に分けられます。
1年未満の貸し出しに対する金利を「短期金利」といい、銀行預金利率の目安になっています。
1年以上の貸し出しに対する金利は「長期金利」といいます。
長期金利は、新規発行10年物国債の利回りなどが指標となり、長期固定金利の住宅ローンや企業融資における金利の目安にもなっています。
長期金利は、変動リスクがあるために、短期金利より高くなっていることが多く、未来の物価変動や景況などに影響を与える事になっています。
賃貸アパートを建設して土地活用するには絶好の機会

日本社会は、
- 輸出型産業の不振
- 個人消費の低迷
- 巨額の財政赤字
- 少子高齢化
といった大きな問題を抱えています。
また、今後の消費税等の増税まで考えると、低金利政策はしばらく続くとみられます。
公定歩合は日本銀行が民間銀行へ貸し付けを行うとき適用される基準金利で、この操作で金融政策を行うことができました。
その公定歩合は、
- 1995年平成7年1月に1.0%、
- 1995年平成7年9月に0.5%
- 2001年平成13年9月に0.1%
- 2008年平成20年に0.3%
となっています。
その後、2016年平成28年1月、日本銀行はマイナス0.1%の金利の適用決定し、長期金利が大幅に低下しました。
さらに、マイナス金利政策を維持した上で、10年物国債利回りを0%程度にする金融緩和政策を発表しました。
現在の金利水準は、かつてないほどの史上最低であり、土地活用によるアパート経営のための、建設費用の借り入れ等、投資タイミングとしては絶好のタイミングといえます。
土地活用オーナーは、今からでも節税対策をしよう








現在、国と地方の長期債務残高は増加の一途で、深刻な状態が続いています。
国家予算の恒常的な赤字は必ず増税に結びつくものです。反面、法人税は国際社会の競争激化に伴い、減税の傾向にあるので、個人の相続税や富裕層への所得税増税となる事が予想できます。
住まいに関する社会の変化を土地活用のヒントに

人口減少と、単身世帯の増加時代に求められる賃貸住宅とは
さらに、夫婦と子供の世帯は、1500万世帯から750万世帯に半減すると予測されています。
まさしく少子高齢化社会であり、賃貸住宅の、メイン客層である若年層が大幅に減少していく傾向にあり、65歳以上の高齢者は、2,924万人で、3,768万人と1.29倍に増加していくと予測されています。
つまり、10人に4人が65歳以上の高齢者、4人に1人が75歳以上という「超高齢化社会」が待っています。
また、夫婦だけで子供がいない世帯は、446万世帯から、780万世帯へと、1.75倍に増加すると予測されています。



高齢者が増え、家族構成に変化があることで、単身者用の住宅、高齢者用の福祉系住宅、つまりコンパクトな部屋の需要が増加していくと予想できます。
こういった時代の変化にこたえられる賃貸住宅を提供出来れば、とても有望な土地活用の一つにもなるはずです。
所得の減少をふまえ、賃料設定を含め収支計画はしっかり
国税庁が毎年発表している「民間給与実態統計調査」によると、バブル崩壊直後の平均給与は年間455万円でした。その後、17年の間、406万円と10.8%も減っています。2016年平成28年では、422万円と微増となっています。
住宅購入の中心世代の年収推移も下降傾向にあり、当然家賃に回す予算も年々減少してきています。
入居者のニーズにマッチした賃貸住宅は、入居者の増加につながります
民間賃貸住宅を含めた住宅市場動向の参考になる平成28年度住宅市場動向調査報告書では入居者がその賃貸住宅を選んだ理由として、
・【家賃が適切だったから】 55.7%
・【住宅の立地環境が良かったから】 47.7%、
・【住宅のデザイン・広さ。設備等が良かったから】 34.0%
となっています。
設備等に関する選択理由では、
・【間取り・部屋数が適当だから」 71.6%
・【住宅の広さが十分だから】 58.5%
「適切な家賃と問取り」を求めるという、費用対効果を重視する堅実な入居者が多いことが分かります。
これは、先ほどの所得の減少という背景が関係があるかもしれません。
入居者の状況が悪くなれば、賃貸住宅経営にもマイナスの影響が表れます。
敷金、礼金、更新料などについては、借り手の事情を反映してか、「なし」の回答が増えています。
特に、礼金については、「なし」との回答が49.9%とほぼ半数を占めました。
所得の減少といった環境変化は土地活用オーナーの努力ではどうすることもできません。
しかし、【満室経営】を実現することでこういった状況に対応することは可能だと考えます。
設備的な充実はしっかり行ったうえで、同じ価格帯のライバル物件よりも、より魅力的な物件にする努力は必要不可欠です。
そういった中で、こういった消費者ニーズの把握をして長期的な計画に反映することも考えましょう。
今後、住宅の建設数は増えていく?減っていく?
1989年平成元年には暦年ベースで166万戸に達した新築住宅着工戸数も、2009年平成21年には史上最低の約79万戸となり、ピーク時の半分以下に落ち込みました。
消費税8%アップヘの駆け込み需要、相続税引き上げ対策としての貸家着工などで、2017年平成29年には約97万戸まで回復しました。
今後は、全国的にみても人口・世帯数ともに減少していくのが基調であるため、住宅建設数は徐々に減少していく傾向にあります。
都市部への人口集中は、しばらく継続すると思われ、首都圏・大都市圏の住宅の需要は横ばいと考えられています。
建設業者が倒産したらお金は戻ってくるの?しっかりリスクマネジメントを。




建設業者と請負契約を締結するときは、その会社の財務状況などの信用調査を十分に行うことが重要です。業界に通じている専門家が間に入り、必要に応じて信用調査会社などに調査を依頼することをお勧めします。
賃貸住宅に長く住む意識変化「仮住まい」ではなくなった。
最近では賃貸住宅への永住意識が高まっていることは、アパート経営で土地活用を考えている方には朗報でしょう。
少子化という日本の状況は、マイナス要素ですが、積極的に賃貸住宅を選ぶという方々の増加はプラス要素です。
2割強の方々が賃貸派と言われています。この理由は、デフレ経済下で地価が下がり続けているため購入は得ではないというものがほとんど。
また、ライフスタイルの変化に合わせて住居を変えたいという人や、特に若い世代では住宅ローンにしばられたくないといった意識も見られます。
『持ち家』がゴールという考え方は、徐々に薄れてきていると考えてよいでしょう。
若者ばかりではなく、高齢者の中でも、自宅老朽化や、夫婦2人でコンパクトな賃貸住宅に住みたい層も増えつつあります。
こうした日本人の住宅への意識が徐々に変化は、アパート経営・マンション経営を検討中の土地活用オーナーにとっては好材料です。
みんなの、賃貸住宅に求める安全はどんなもの?
これからの賃貸住宅は、地震や津波、洪水といった自然災害への対策も十分に検討しておくことが求められます。
当然、建物の性能だけではなく、災害時でも、電気・水道・通信といった生活インフラをどのように確保するかも、これからの賃貸住宅では検討が求められる事になります。
賃貸住宅を探す際は、家賃と鉄道路線、最寄り駅からの時間が最も重要視され、この傾向は今もほとんど変化がありませんし、今後もしばらくは変わらないでしょう。
ただ、キッチンやお風呂、 トイレなどの設備・仕様を重視する割合が大幅に増加しています。
今までの賃貸住宅では考えられなかったような設備、追い焚き機能付浴室、システムキッチン、浴室換気乾燥機、床暖房などが上位にランキングされているのは、「長く快適に賃貸住宅に住みたいユーザー」が増えていることだろうと考えられます。
こういった中、高齢者に向けた、手すりや、入りやすい浴槽、車いすで通行ができる廊下、段差のない屋内等、バリアフリー設備がある住宅は48.7%も増えてきています。
東日本震災を契機にして太陽光発電電力の固定買い取り制度がスタートしたこともあり、太陽光発電システムを備えた住宅は2013年平成25年時点には156万戸を突破しましたが、全住宅の中で占める比率は3.0%、借家に限れば0.5%とまだまだ低い数値となっています。
まずは心構えが大事!なぜ土地活用をするのかを明確に。遊休地を土地活用して、収益化資産にできたら、夢のオーナーズライフが送れちゃうなー。そんな甘い考えではいけません!収益を得るということは、[…]