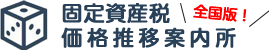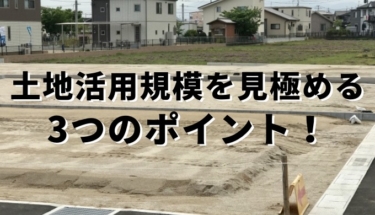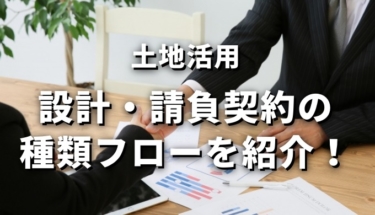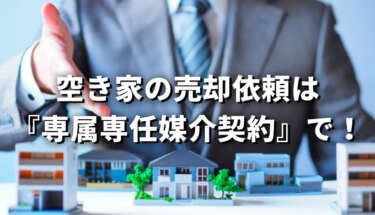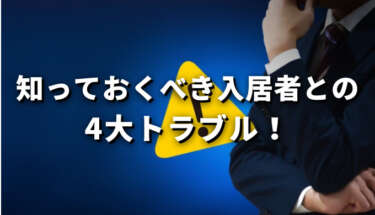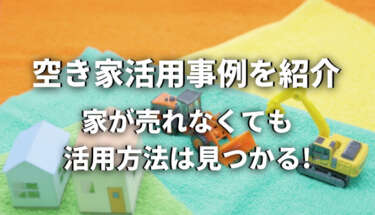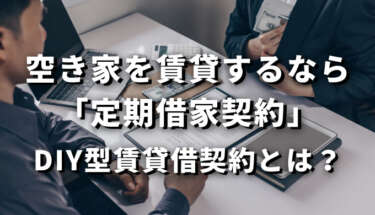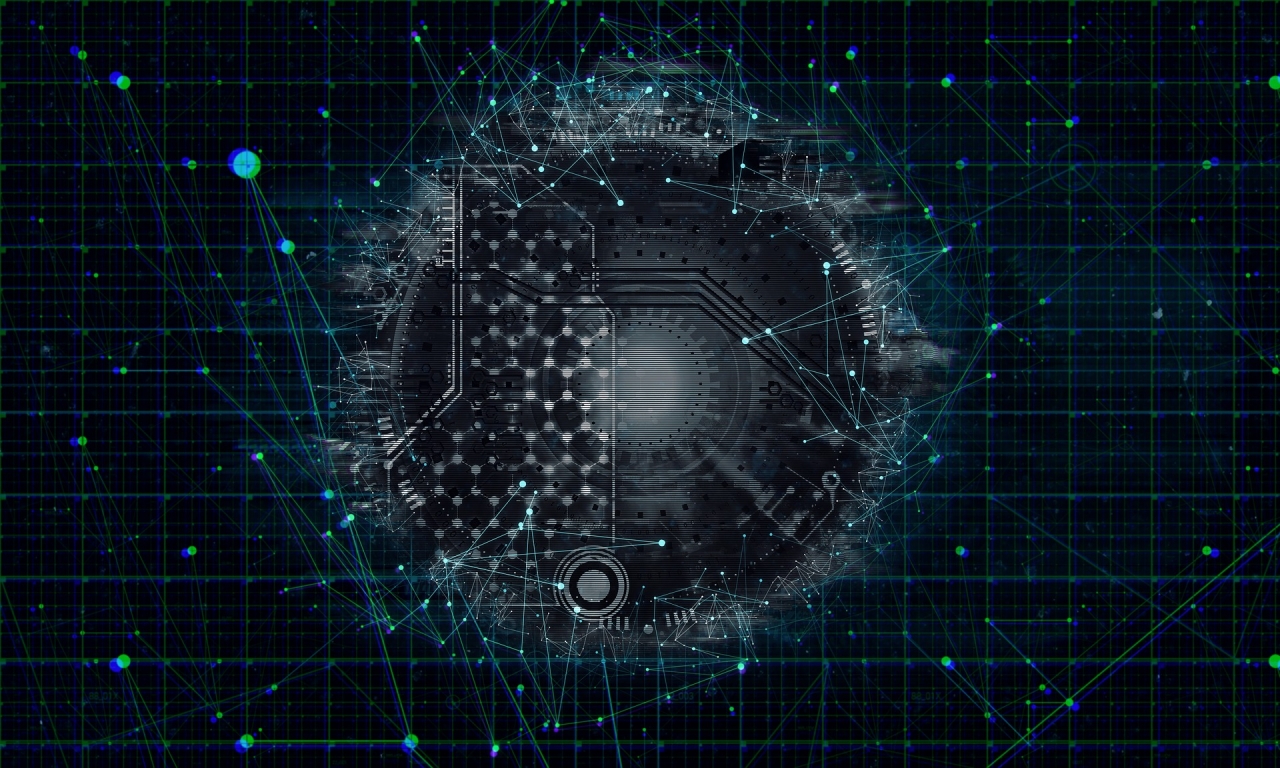土地活用で賃貸マンションを建てようと思ってるんだけど、建築費が適正価格なのかどうかがわからなくて困ってるんだよね。

建築費は坪単価で比較するといいよ。
今回は、建築費の目安について紹介しよう。
今回は、建築費の目安について紹介しよう。
建築費の坪単価とは?

土地活用における建築費の坪単価には、3つの種類があります。
それは、建築費の坪単価を①専有面積で計算するのか、②法廷床面積で計算するのか、③施工床面積で計算するのかということです。
それは、建築費の坪単価を①専有面積で計算するのか、②法廷床面積で計算するのか、③施工床面積で計算するのかということです。
①専有面積で計算
専有面積とは、賃貸可能面積のことです。
建築費用が1億円で専有面積が100坪の場合、坪単価は100万円となります。
建築費用が1億円で専有面積が100坪の場合、坪単価は100万円となります。
②法廷床面積で計算
法廷床面積とは、「専有面積」に「法定共用部分(容積率にカウントされる法令上の共用面積)」をプラスした面積のことです。
建築費用が1億円で法廷床面積が120坪の場合、坪単価は83万円となります。
建築費用が1億円で法廷床面積が120坪の場合、坪単価は83万円となります。
③施工床面積で計算
施工床面積とは、実際に工事される面積(「専有面積」「法定床面積に入る共用部分の面積」「法定床面積以外の共用部分の面積」の合計)のことです。
建築費用が1億円で法廷床面積が150坪の場合、坪単価は67万円となります。
建築費用が1億円で法廷床面積が150坪の場合、坪単価は67万円となります。

同じ建築費用であっても、どの面積の坪単価なのかを計算すると、坪単価は変わってくるんだね。

建築費用として費用を検討するのではなく、各面積の坪単価を計算することで適正価格かどうか判断するようにしよう。
建物構造による坪単価の目安から建築費用を計算しよう!

建物の基本設計図ができると、設計の図面から概算の建築費用が計算できます。
建物構造(木造建物なのか鉄骨建物なのかなど)によって建築費用の坪単価は変わってきますので、坪単価の目安を紹介しますので参考にしてみてください。
木造建物の場合
単価の幅は施工条件と設備仕様によって決まるのですが、木造で低価格路線の工務店に依頼する場合は法廷床面積の坪単価50万円が一般的です。
大手ハウスメーカーなどに依頼し、仕様や設備にこだわった建物を建築するとなると、法廷床面積の坪単価は80万円以上になることもあります。
大手ハウスメーカーなどに依頼し、仕様や設備にこだわった建物を建築するとなると、法廷床面積の坪単価は80万円以上になることもあります。
木造建物の坪単価の目安
法廷床面積の坪単価50~80万円が目安
鉄筋コンクリート造建物の場合
鉄筋コンクリート造の場合は、基礎工事の内容や建設会社の規模(スーパーゼネコン、準大手、上場会社、中堅会社など)、建物のグレード、構造(ラーメン構造、壁構造など)、建築する階数、建物全体のボリュームによって金額が変わってきます。
鉄筋コンクリート造建物の坪単価の目安
法廷床面積の坪単価80~100万円が概算工事費の目安
鉄筋コンクリート造の場合、建築する建物によって工事費の幅が大きくなるため、目安となる坪単価とは異なることもあります。
鉄骨造建物の場合
鉄骨造建物の場合、鉄筋コンクリート造と同じくらいの坪単価となることが多いです。
しかし、鉄骨材の価格動向によって建築費が大きく左右されてしまいます。
鉄骨造建物の坪単価の目安
法廷床面積の坪単価80~100万円が概算工事費の目安
基本設計図で建築費を計算する場合、建築費用を安く考えてしまうと、後々建築費用が高くなることもあるので要注意です。
基本設計図段階では、建築費用を少し高めに設定しておき、その後必要なものを絞り込んで費用のスリム化を目指していくことがオススメです。
基本設計図段階では、建築費用を少し高めに設定しておき、その後必要なものを絞り込んで費用のスリム化を目指していくことがオススメです。
建築費用は変動することを覚えておく!


基本設計段階で、計算した建築費用は変動することがあるので覚えておこう。
それじゃあ、変動する要因について紹介するよ。
それじゃあ、変動する要因について紹介するよ。
建築費用の変動要因
- 地盤状況によって基礎工事費用に追加費用がかかる
- 地中障害物がある場合に解体工事費用がかかる
- 地震対策の工事費用がかかる
① 地盤状況で変わる基礎工事費用
地盤の状況によって基礎工事の内容が大きく変わってきます。
建築費用を確定するためには、地盤調査をしっかり行うことが重要となります。
建築費用を確定するためには、地盤調査をしっかり行うことが重要となります。
基礎工事の種類
- ベタ基礎
- 地盤改良をして地盤強化しベタ基礎
- 杭を打つ など
必要な基礎工事は、地盤の状況と建物の重量や形状によって変わります。

それぞれの基礎工事費用は大きく違ってくるから、建築費用は地盤状況によって大きく変化するんだよ。
基礎工事費用を知るためには?
基礎工事の大体の費用を知るためには、周辺建物の基礎状況を参考にすることがあります。
ボーリングデータを持っている設計事務所や建設会社であれば、周辺の地盤状況を把握することができます。
ボーリングデータを持っている設計事務所や建設会社であれば、周辺の地盤状況を把握することができます。
地盤が緩い地域で、周辺建物が30mまで杭を打っている場合は、それを基にした基礎計画となります。
地盤が強い地域で、低層型建物(3階建以下)を建設する場合は、基礎工事はベタ基礎となります。
地盤が強い地域で、低層型建物(3階建以下)を建設する場合は、基礎工事はベタ基礎となります。
② 地中障害物の解体工事費用
古井戸や既存建物の地下室、基礎、杭などの地中障害物が地中に埋まっている場合、撤去する必要があります。
地中障害物は、掘ってみないと分からず、見積書では別途工事となります。
地中障害物は、掘ってみないと分からず、見積書では別途工事となります。
土地オーナーは見積書を鵜呑みするのではなく、追加工事が発生する可能性があることを理解しておきましょう。
③ 地震対策の工事費用
土地オーナーが建物を耐震構造、制震構造、免震構造と要望する場合に、建築費用が変わってきます。
建物の構造や基礎工事にも影響を与えるため、建築費用も大きく変動してしまいます。
基本設計段階から、地震対策として工事費用を追加するのか検討する必要があります。
建物の構造や基礎工事にも影響を与えるため、建築費用も大きく変動してしまいます。
基本設計段階から、地震対策として工事費用を追加するのか検討する必要があります。

建築費用は非常に大きな金額になるから、必要なものを削らないようにするためにも、土地オーナー自身が建築費用について見極める目が必要となるんだよ。